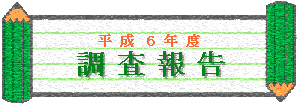
1.はじめに
次の2種類の調査を行いました。
・鬼怒川中流域におけるカゲロウ類の発生状況について
・鬼怒川上・中流域における幼虫の生息状況について
2.鬼怒川中流域におけるカゲロウ類の発生状況について
 目的
目的

栃木県のほぼ中央を流れる鬼怒川において、1978年と1979年の9月に「アミメカゲロウ(Ephoron shigae Takahashi)」が大量羽化しました。我々は昨年までそのアミメカゲロウを中心に調査を行ってきましたが、今年はそれ以外の水生昆虫についても発生状況の調査を行うことにしました。
 調査対象とした水生昆虫
調査対象とした水生昆虫

昨年まで調査対象の中心でだったアミメカゲロウの他、チラカゲロウ、エルモンヒラタカゲロウ、キイロカワカゲロウ、ムスジモンカゲロウ、ヒゲナガカワトビケラの6種。
 調査場所
調査場所

栃木県宇都宮市石井町の新鬼怒橋下の河原(下図参照)において調査を行いました。
<図1> 調査場所の位置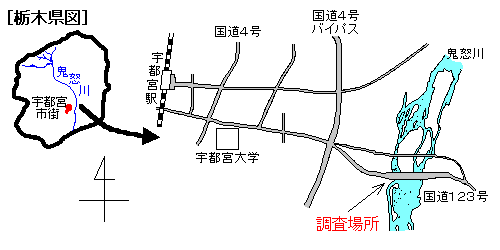 |
<図2> 調査場所の様子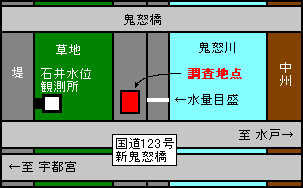 |
 調査方法
調査方法

<図3> ライトトラップ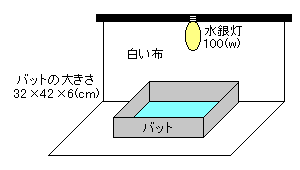 |
4月~12月の間、1週間に1度くらいの割合で日没前後の1時間、ライトトラップによる調査を行いました。ライトトラップとは、水銀灯を点灯させその光に集まる昆虫を採集する方法で、図のように水銀灯の後ろに白い布、下にアルコールを浸したバット(容器)を置き、その中に落ちた昆虫を採取しました。それと並行して周辺に集まる昆虫の様子・種類・量等を観察し、調査時の気温・水温・水量・天候も記録しました。水量については河原の土手に設置された水位観測目盛りを読み取りました。
 結果
結果

<図4> 気温と水温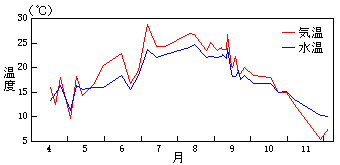 |
4月~12月にかけて計37回の調査を行いました。9月中はアミメカゲロウの発生状況を詳しく調査するために12回行いました。調査時における気温・水温の変化は図4の通りです。次で各種の発生状況について水量の変化とあわせてグラフ化しました。
 チラカゲロウ(採取数:32968)
チラカゲロウ(採取数:32968)
<図5> 水量とチラカゲロウの発生状況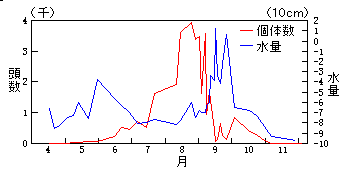 <図6> チラカゲロウの雌雄別発生状況 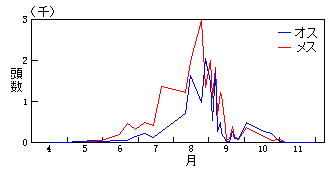 <図7> チラカゲロウの成虫・亜成虫別発生状況 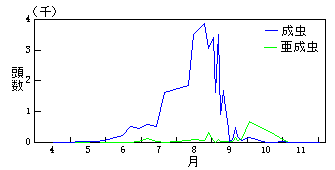 |
年2世代のカゲロウといわれていますが、図5を見て分かるように長期にわたり発生していたため、年1世代とも言える結果となりました。水量の変化との関連性は見つけられませんでした。
図6より、オスよりもメスの発生量の方が多いことが分かりました。
図7より、9月の下旬までは成虫の方が多く、10月に入ると亜成虫の方が多くなっていました。
 エルモンヒラタカゲロウ(採集数:14049)
エルモンヒラタカゲロウ(採集数:14049)
<図8> 水量とエルモンヒラタカゲロウの発生状況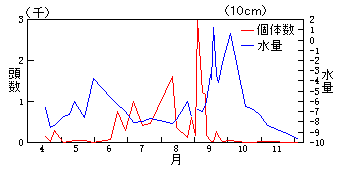 <図9> エルモンヒラタカゲロウの雌雄別発生状況 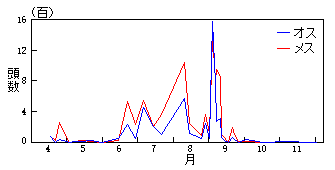 |
本種は5~8月と9~11月に発生する年2世代のカゲロウです。
図8より、6月中旬~8月中旬に1世代目、9月頃に2世代目が発生しているようにも見えますが、はっきりとしたことは確認できませんでした。また、水量が増加したときに発生量が減少していました。水量の多かった5月下旬・9月上旬・10月上旬にはほとんど発生していませんでした。
図9より、チラカゲロウ同様オスよりもメスの発生量の方が多くなりました。
 キイロカワカゲロウ(採取数:7305)
キイロカワカゲロウ(採取数:7305)
<図10> 水量とキイロカワカゲロウの発生状況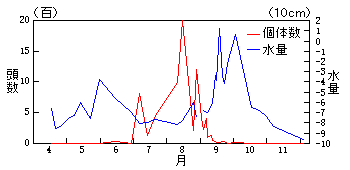 |
初夏から秋にかけて発生する年1世代のカゲロウです。今回の調査でも6月~9月頃まで発生が見られました。また、エルモンヒラタカゲロウと同様に水量が増加したときに発生量が減少していました。
 ムスジモンカゲロウ(採取数:1782)
ムスジモンカゲロウ(採取数:1782)
<図11> 水量とムスジモンカゲロウの発生状況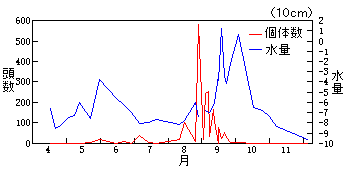 |
春から夏にかけて発生する年1世代のカゲロウです。今回の調査でも5月下旬~10月上旬まで発生が見られました。発生のピークは8月下旬~9月上旬でした。また、水量増加時には発生量が減少していました。
 アミメカゲロウ(採取数:9)
アミメカゲロウ(採取数:9)
<図12> アミメカゲロウの発生状況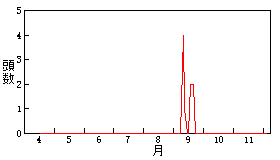 |
発生のピークと思われる時期に悪天候により調査を行うことができませんでした。発生時期は昨年の結果とほぼ同じでしたが、確認頭数は昨年の4分の1程度でした。
 ヒゲナガカワトビケラ
ヒゲナガカワトビケラ
<図13> ヒゲナガカワトビケラの発生状況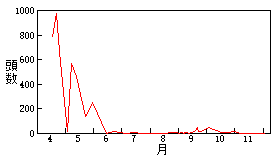 |
調査を開始したときに特に目立っていたため、この種についても発生状況を調べました。
 考察
考察

 チラカゲロウとエルモンヒラタカゲロウの発生状況について
チラカゲロウとエルモンヒラタカゲロウの発生状況について
今回の調査では年2回発生する様子は確認できませんでした。これを調べるにあたっては、幼虫の調査を並行して行う必要があり今後の調査に期待したいです。
 水量と発生量の関連性について
水量と発生量の関連性について
エルモンヒラタカゲロウ・キイロカワカゲロウ・ムスジモンカゲロウについては、水量が減少したときに発生量が増加する傾向が見られました。しかし、グラフでは水量が増加しているように見えても実際には減少している途中であるということも考えられ、今回のデータだけでは関連があるかどうかは判定できないため、今後詳しく調査していきたいと考えています。
 成虫と亜成虫の比率について
成虫と亜成虫の比率について
図7を見ると4月~9月までは成虫の割合の方が圧倒的に多く10月に入るとそれが逆転しているのがわかります。しかし、現状では他の種や前年の調査との比較ができないため、今後もデータを集めていく必要があると考えます。
 オスとメスの比率について
オスとメスの比率について
図6・図9を見ると、オスよりもメスの発生量の方が多いことがわかります。ただし、9月上旬はオス・メスともに同じくらいの割合で確認されており、今回の調査だけでは何とも言えませが、「メスの方が光りに集まりやすい」「メスの方が数が多い」「メスの方が寿命が長い」等、何らかの理由が考えられるのではないでしょうか。
3.鬼怒川上・中流域における幼虫の生息状況について
 目的
目的

水生昆虫の生態についてより深い理解を得るために、幼虫期の生態についても知る必要があると考えました。とりあえず今年は次の2点を調査の目的としました。
・定量的調査法を試行することで、幼虫の採集方法や生活環境について知る。
・鬼怒川に生息している幼虫の種・頭数・生息地域などを調べ、幼虫の生息分布について知る。
 調査地点
調査地点

自家用車で進入可能な鬼怒川の最上流地点から成虫の調査を行った新鬼怒橋との間に約10kmおきに9ヶ所の調査地点を設定し、上流から順にA~Iまでのアルファベットで表しました。
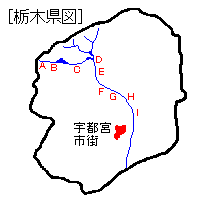 |
|
 調査日時
調査日時

A・D・E地点は8月16日、B・C・F・G地点は8月17日、H・I地点は8月25日に調査を行いました。調査時間は午前10時~夕方にかけての間です。
 調査方法
調査方法

各調査地点において河原に近い流れの緩やかなところと、川の中心付近の流れの速いところの2ヶ所でコドラート法を行いました。
水底に50cm×50cmの正方形の枠(コドラ-ト)を定めて、その面積内の水生昆虫を採集する方法で、面積内にある石などをすべて取り上げ、これらに付着している水生昆虫を採取しました。更に石を持ち上げる際に水中に落ちてしまった昆虫を捕らえるため、コドラートの下流側にネットを張り、その中に流れ込んだ昆虫も採取しました。
 調査結果・考察
調査結果・考察

 調査地点について
調査地点について
河原の広さや石の大きさ、水温、水量・流速などには違いがあるため、採取される種類や数に片寄りが出てしまうのではないかと心配していましたが、最初に述べた目的を達成できるだけのデータは得られました。しかし、中には明らかに不自然な結果の出た調査地点もあったので、その理由について考察します。
【 B地点 】
川俣湖の西端部に位置し、本来なら湖の底に当たる場所です。しかし、干ばつにより水位が極端に下がり、調査時には湖底が露出し、湖に流れ込む水が細い川のようになっていました。川底には砂や泥が堆積しており、他の調査地点の川底とはまったく違った様相を見せていました。ここでは水生昆虫を全く採取することができず、コドラート外にある石も取り上げてみましたが、やはり水生昆虫のいる気配はありませんでした。その理由として、この地点は調査時こそ川の流れが存在していたものの、かつては止水域(湖底)であったため、水の流れのあるところを好んで生活する水生昆虫にとって生息できる環境ではなかったということが考えられます。
【 D地点 】
川治ダムより1km程下流に行った所です。川底の様子は他の調査地点とあまり変わらず、水も比較的澄んでいました。しかし、採取された幼虫は2頭だけと、周辺の地点に比べ非常に少ない結果となりました。その理由として、この付近の河原には、流れに沿うようにして川の石が高く積まれ、その外側にはコンクリートの舗装がしてあり、明らかに人間の手が加えられた形跡が見られました。このことにより水生昆虫にとって住みやすい環境が破壊されてしまい、そこに生息していた幼虫の数が激減してしまったと考えられます。
 採集された昆虫について
採集された昆虫について
種の特定ができなかったもの(34頭)も含め、30種以上計833頭の水生昆虫を採取しました。目別に分類すると、カゲロウ目・トビケラ目・カワゲラ目・双翅目・トンボ目の5目に分けられました。双翅目(全てサナギの状態)とトンボ目については種の特定ができなかったため、今回は詳しく触れないことにしました。
各調査地点で2ヶ所のコドラートを設定し、それぞれで採集された頭数の和を各調査地点の総数としました。B地点については、採取数0なので表に載せていません。
 カゲロウ目(約20種559頭、全体の約68.3%)
カゲロウ目(約20種559頭、全体の約68.3%)
【 ヒラタカゲロウ科 】
<表A> ヒラタカゲロウ属 A C D E F G H I 計 エルモンヒラタカゲロウ 18 5 2 56 22 195 8 296 タニヒラタカゲロウ 8 1 6 3 2 20 ナミヒラタカゲロウ 2 2 ウエノヒラタカゲロウ 9 9 ユミモンヒラタカゲロウ 11 11 オナガヒラタカゲロウ 1 1 計 47 8 0 2 56 28 198 10 339 カゲロウ目の中でも最も採集頭数が多かった種です。特にエルモンヒラタカゲロウが多く、これは成虫の調査結果とも結びつきます。ユミモンヒラタカゲロウのように川の上流域にしか生息していない種と、エルモンヒラタカゲロウのように上・中流域にかけて広範囲に生息している種がある事が分かりました(表A)。
<表B> タニガワカゲロウ属 A C D E F G H I 計 シロタニガワカゲロウ 1 20 28 45 28 7 129 ミヤマタニガワカゲロウ 28 28 計 0 0 1 20 28 45 56 7 157 それに対してタニガワカゲロウ属は、下流に行くにしたがって採取量が増加していました(表B)。これは、本属が比較的流れの緩やかなところを好んで生息している種であるためと思われます。
<表C> ヒメヒラタカゲロウ属 A C D E F G H I 計 サツキヒメヒラタカゲロウ 1 1 ヒメヒラタカゲロウ属は、鬼怒川上・中流域にはあまり生息していないことが分かりました(表C)。
【 マダラカゲロウ科 】
<表D> マダラカゲロウ属 A C D E F G H I 計 トウヨウマダラカゲロウ 1 1 ヨシノマダラカゲロウ 8 8 クロマダラカゲロウ 1 1 ミツトゲマダラカゲロウ 1 1 2 アカマダラタカゲロウ 7 4 3 14 チェルノバマダラタカゲロウ 1 2 3 不明 1 12 13 計 1 10 0 0 8 7 17 0 42 マダラカゲロウ属1属しか知られていませんが、採集された種はカゲロウ目の中で最多でした。しかし、採取量が少なく、採取地点にもばらつきがあったため、はっきりとした考察は立てられませんでしたが、鬼怒川上・中流域において広く分布している科であることは分かりました(表D)。
【 トビイロカゲロウ科 】
<表E> ヒメトビイロカゲロウ属 A C D E F G H I 計 ヒメトビイロカゲロウ 1 1 ヒメトビイロカゲロウが1頭のみ採取されました(表E)。今回の調査地域にはほとんど生息していない種であることが分かりましたが、本来は河川の中・下流域の比較的水の汚れているところに生息している種なので、さらに下流域では多く生息していることも考えられます。
【 チラカゲロウ科・カワカゲロウ科 】
<表F> チラカゲロウ属・カワカゲロウ属 A C D E F G H I 計 チラカゲロウ 2 12 14 キイロカワカゲロウ 3 1 4 チラカゲロウとキイロカワカゲロウは1属1種のカゲロウです。H地点などで採集されました(表F)。この2種について、成虫の確認数に比べ幼虫の確認数が非常に少なかった理由として次のようなことが考えられます。
カゲロウの幼虫の生活形態次の3タイプに分類できます。
①川底に穴を掘ってその中で生活しているタイプ・・・カワカゲロウ科
②水中を自由に泳ぎ回ることのできるタイプ・・・チラカゲロウ科
③川底の石などに張り付いて歩き回りながら生活しているタイプ
今回の調査方法だと、コドラート内にいる①②のタイプの幼虫を捕らえることは困難であったことによりこのような結果になったと考えられます。
 トビケラ目(3種174頭、全体の約21.4%)
トビケラ目(3種174頭、全体の約21.4%)
他のの2目の幼虫と比べると非常に独特な体型をしているため、容易に見分けがつきます。採集量が多い割には種が少ない結果となりました。
【 ヒゲナガカワトビケラ科・シマトビケラ科 】
<表G> ヒゲナガカワトビケラ科・シマトビケラ科 A C D E F G H I 計 ヒゲナガカワトビケラ 27 4 24 5 43 4 103 チャバネヒゲナガカワトビケラ 1 1 2 ウルマーシマトビケラ 10 2 56 1 69 計 37 4 0 0 27 5 100 5 174 ヒゲナガカワトビケラ科は日本で最も大型のトビケラであり、生息数も多いことが知られています。鬼怒川でもそれは例外でなく上・中流域に広く分布していることが分かりました。
チャバネヒゲナガカワトビケラはヒゲナガカワトビケラと非常によく似た外見をしているため、同定ミスの可能性も考えられます。
シマトビケラ科は、日本の河川に最も優占的に生息している種で、その中でも最も普通種であるのがウルマーシマトビケラです。しかし、今回の調査結果から、鬼怒川上・中流域においてはヒゲナガカワトビケラの方が優占的に生息していることが分かりました。これは成虫の調査結果からも言えることでです。
 カワゲラ目(6種30頭、全体の約3.6%)
カワゲラ目(6種30頭、全体の約3.6%)
採集量は少なかったが、日本全土に分布しており、現存する有翅昆虫のうちで最も原始的な昆虫の1つです。
【 カワゲラ科 】
<表H> カワゲラ科 A C D E F G H I 計 オオヤマカワゲラ 1 12 3 2 5 23 ヒメオオヤマカワゲラ 1 1 カミムラカワゲラ 1 1 オオクラカケカワゲラ 1 1 ヒトホシクラカケカワゲラ 1 1 不明 3 3 計 1 4 1 0 12 4 3 5 30 今回採集されたカワゲラのうち最も多かったのは「オオヤマカワゲラ」でした。本種は日本で最も大型のカワゲラの1つです。その他のカワゲラ属については、クラカケカワゲラ属、カミムラカワゲラ属が採集されましたが数は少なく、鬼怒川上・中流域においては、オオヤマカワゲラが最も優占的に生息していることが分かりました。
4.おわりに
今年の調査内容は我々班員にとって初めての経験であったため、どのような結果が得られるのか予想がつかず手探り状態での調査となってしまいました。成虫の調査については9月上旬の天候が悪く、思うように調査が行えなかったためにその間のデータが不足してしまったことが非常に悔やまれる点です。幼虫の調査についても最初に計画を立てた時点でもう少し調査内容等について話し合い、検討を重ねていれば更に充実したデータが得られたと思われます。しかし、今回は幼虫の調査を2日間の合宿という形で行ったことは班員相互の理解を深める上で非常に有意義なものでありました。また、採取したアルコールづけの昆虫が想像以上に膨大な量となってしまい、その中から研究対象であるカゲロウを同定・カウントする作業に多大な労力を費やすこととなってしまったことも反省すべき点でした。このようにさまざまな問題点が生じたにせよ、成虫・幼虫の調査共に、始めに立てた目標をある程度達成できたことについては班員共々喜ばしく思っています。今年明らかになった問題点については、検討を重ね今後の活動に役立てていきたいと考えています。
最後になりましたが、生物研究会顧問の中村先生をはじめ、ご協力いただいた皆様に感謝の意を表し、終わりとさせていただきます。