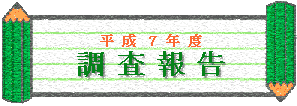
1.はじめに
以下の4つのテーマを定め、鬼怒川において調査しました。また、昨年度行った幼虫の生息調査範囲よりもさらに上流部において幼虫を採集しました。
①鬼怒川中流域における発生状況について
②飛来数の変化と時刻の関係について
③水位の変化と発生量の関係について
④エルモンヒラタカゲロウの年2回発生について
これらの調査結果を次に報告します。
2.カゲロウ類の紹介
 アミメカゲロウ(蜉蝣目アミメカゲロウ科アミメカゲロウ属)
アミメカゲロウ(蜉蝣目アミメカゲロウ科アミメカゲロウ属)
9月の中旬に集中して羽化する年1回発生。日本各地で発生の記録はあるが、阿武隈川(福島県)、那珂川(茨城県)を除く各地で発生するのは雌のみ。
【 成虫の特徴 】
体長9mm前後。尾は雄が2本、雌が3本。全体に白っぽく、肢が貧弱で体を支えることができない。
【 幼虫の特徴 】
体長12mm前後。大型のもので20mm。掘潜型で、早瀬の石の下の安定した砂泥中に巣穴を掘って生息。
 チラカゲロウ(蜉蝣目チラカゲロウ科チラカゲロウ属)
チラカゲロウ(蜉蝣目チラカゲロウ科チラカゲロウ属)
5~6月、9~10月に羽化する年2回発生。山地渓流から平地の流れにかけて広く見られる。本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長16~18mm。尾は2本。頭部は光沢のある黒色、胸部と腹部は濃い褐色。
【 幼虫の特徴 】
体長18mm位。尾は3本。全体が黒褐色で、水中を自由に泳げる円筒形。
 エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
晩春から初夏、初秋から晩秋にかけて羽化する年2回発生。羽化直前になると川底から離れ、水面に浮かび出てくると背中が裂けてパッと羽化する。山地渓流から平地の流れにかけて広範囲に見られる。北海道・本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長9~10mm。尾は2本。全体が薄黄色をおび、翅の付け根にL(エル)の紋がある。
【 幼虫の特徴 】
体長10~15mm。尾は2本。偏平な形で、川底の石について生息。鰓の半分以上に大小赤紫の点紋が散在。
 キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
6~8月に羽化する年1回発生。北海道・本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長10~11mm。尾は3本。全体が黄色をおび、翅は無色透明だが、前翅の前縁に褐色の部分がある。
【 幼虫の特徴 】
体長8~10mm。尾は3本。全体が淡黄褐色で、緑褐色の斑紋があり、体型は細長くやや円筒形。低山地や平地の流水の緩やかな部分の石の下に生息。
 ムスジモンカゲロウ(蜉蝣目モンカゲロウ科モンカゲロウ属)
ムスジモンカゲロウ(蜉蝣目モンカゲロウ科モンカゲロウ属)
4~5月、8~9月に羽化する。本州・四国・中国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長13~17mm。尾は3本。全体が黄白色をおび、腹節には2~3対の黒色の縦状紋がある。羽は無色透明で、前翅中央に黒褐色の斑紋がある。
【 幼虫の特徴 】
体長20mm。尾は3本。腹部背面に斑紋が3対縦状にある。平地の流水及び浅い湖沼の砂泥低に埋もれて生息。
 ヒゲナガカワトビケラ(毛翅目ヒゲナガカワトビケラ科)
ヒゲナガカワトビケラ(毛翅目ヒゲナガカワトビケラ科)
4月末~10月末に羽化し、河川の上流から下流まで広く生息する。北海道・本州・四国・九州に分布する。
【 成虫の特徴 】
体長約20mm。尾はない。頭胸部、前翅は暗褐色である。触覚が前翅長より長いので(時に雄は1.5倍ある)この名がついた。
【 幼虫の特徴 】
体長30~40mm。全体が黒褐色で光沢があり、体型は長い円柱状である。礫底の川に生息し、礫の裏側に口から糸を出して網を張り、固着巣を作成する。
3.鬼怒川中流域におけるカゲロウ類の発生状況について
 目的
目的

年間を通してカゲロウ類の発生状況を把握し、昨年の発生状況と比較する。
 まえおき
まえおき

調査を始めて2年目の今年は、昨年の発生時期との違いについて比較することも考えました。また、この調査で得られた結果は、同時進行で行った他の調査に必要とされるため、今年の活動の中心となりました。
 調査場所
調査場所

栃木県宇都宮市石井町の新鬼怒橋下(鬼怒川石井水位観測所付近)の河原において調査を行いました。
<図1> 調査場所の位置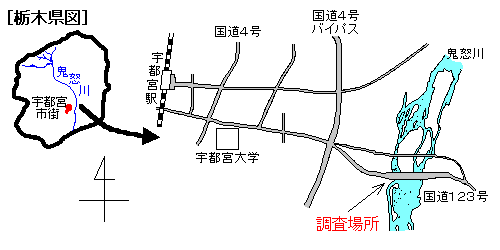 |
<図2> 調査場所の様子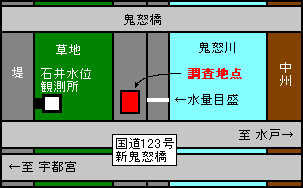 |
 調査時間
調査時間

1月~11月にかけて、日没から1時間調査を行いました。1月~3月は月に1回、4月からは週に1回、9月のみアミメカゲロウの発生時期と重なるため3日に1回の割合で調査を行いました。
 調査方法
調査方法

<図3> ライトトラップの装置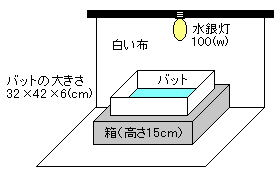 |
調査はライトトラップにより行いました。図3のように水銀灯の後ろに白い布、下にアルコールを入れたバット(容器)を置き、その中に落ちたカゲロウ類を採集しました。今年は、バット外に落ちたカゲロウ類が再びバットの中に飛び込むのを防ぐために、下に箱を置いてバットの位置を高くしました。
 結果
結果

1月~11月までに、計36回調査を行いました。昨年の発生状況についてもあわせて比較しました。
 気温・水温
気温・水温
調査時に測定した気温と水温です。
| <表1> 気温と水温(℃) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 気温 | 水温 | 調査日 | 気温 | 水温 | 調査日 | 気温 | 水温 |
| 1月29日 | 4.9 | 7.7 | 6月18日 | 19.5 | 15.4 | 9月20日 | 17.4 | 18.2 |
| 2月26日 | 6.6 | 8.4 | 6月22日 | 15.8 | 14.9 | 9月22日 | 18.9 | 18.2 |
| 3月21日 | 11.4 | 10.8 | 7月06日 | 19.7 | 16.9 | 9月25日 | 25.0 | 21.3 |
| 4月01日 | 8.4 | 9.8 | 7月20日 | 21.7 | 18.6 | 9月28日 | 19.5 | 20.0 |
| 4月13日 | 11.1 | 12.5 | 8月07日 | 26.9 | 24.0 | 10月07日 | 15.6 | 17.8 |
| 4月20日 | 10.0 | 12.5 | 8月23日 | 26.6 | 22.2 | 10月16日 | 20.4 | 18.1 |
| 4月30日 | 19.3 | 16.9 | 9月01日 | 24.7 | 21.9 | 10月22日 | 17.4 | 17.3 |
| 5月07日 | 15.2 | 15.8 | 9月04日 | 23.8 | 20.5 | 10月28日 | 13.5 | 15.8 |
| 5月17日 | 16.8 | 13.8 | 9月07日 | 23.1 | 21.1 | 11月04日 | 15.3 | 15.7 |
| 5月22日 | 9月10日 | 24.3 | 20.9 | 11月12日 | 9.9 | 13.2 | ||
| 5月28日 | 17.8 | 16.5 | 9月13日 | 21.3 | 21.2 | 11月20日 | 9.4 | 12.7 |
| 6月07日 | 16.7 | 17.9 | 9月17日 | 16.2 | 16.5 | 11月27日 | 6.0 | 11.2 |
 カゲロウ類の総数(採取数:19477頭、昨年対比:32%)
カゲロウ類の総数(採取数:19477頭、昨年対比:32%)
<グラフ1> カゲロウ類全体の発生状況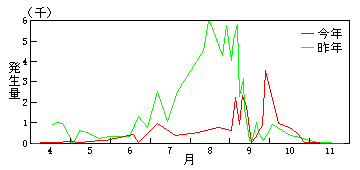 |
発生状況については、昨年のものとあわせて右のグラフ1の通りです。
グラフ1より、発生の期間は昨年とほぼ同じで4月~10月にかけてですが、7月~8月にかけての発生量は昨年に比べ、非常に少ない結果となりました。また、昨年&今年ともに9月の中旬に発生量が激減していました。
 チラカゲロウ(採取数:13866頭)
チラカゲロウ(採取数:13866頭)
<グラフ2> チラカゲロウの発生状況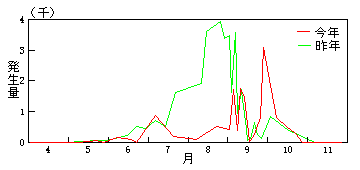 |
昨年の発生量(32968頭)と比べると半数以下でした。
グラフ2より、10月初旬の発生量については、昨年&今年ともに増加していましたが、8月中の発生量については、昨年は増加・今年は減少という結果になりました。発生の時期は昨年とほぼ同じでした。年2回発生の様子については、6月~7月が1回目、9月~10月が2回目といったように、昨年の結果よりははっきりと現われました。
 エルモンヒラタカゲロウ(採取数:4526頭)
エルモンヒラタカゲロウ(採取数:4526頭)
<グラフ3> エルモンヒラタカゲロウの発生状況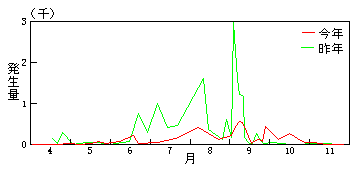 |
発生状況はグラフ3の通りです。本種は、5月~8月上旬と、9月~11月にかけて年2回発生するといわれていますが、昨年と同様にはっきりとしたことは確認できませんでした。発生量が増加した時期(6月上旬&9月上旬)は、昨年の結果とほぼ一致しました。
 キイロカワカゲロウ(採取数:328頭)
キイロカワカゲロウ(採取数:328頭)
<グラフ4> キイロカワカゲロウの発生状況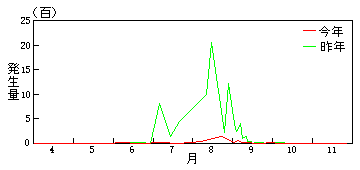 |
昨年と今年の発生状況はグラフ4の通りです。昨年と同様6月~9月に発生が見られましたが、発生のピークは昨年が8月中旬なのに対し、今年は8月下旬となりました。
 ムスジモンカゲロウ(採取数:47頭)
ムスジモンカゲロウ(採取数:47頭)
<グラフ5> ムスジモンカゲロウの発生状況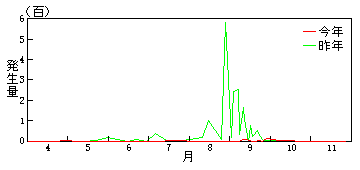 |
発生状況はグラフ5の通りです。今年、本種が最も多く確認された日の頭数は、12頭なのでグラフにはあまり現れていません。9月~10月にかけて多く発生していました。
 ヒゲナガカワトビケラ(採取数:710頭)
ヒゲナガカワトビケラ(採取数:710頭)
<グラフ6> ヒゲナガカワトビケラの発生状況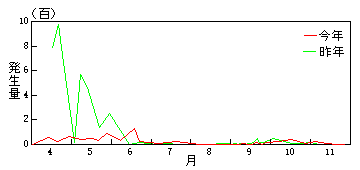 |
発生状況はグラフ6の通りです。発生の時期は昨年とほぼ一致しましたが、発生量については20%にも満たない結果でした。また、4月~6月と9月~10月にかけて多く発生するということは昨年と同じですが、春の発生量は昨年に比べ激減しました。
 アミメカゲロウ(採取数:0頭)
アミメカゲロウ(採取数:0頭)
昨年は9頭を確認することができましたが、今年は1頭も確認することができませんでした。
 まとめ
まとめ

<グラフ7> 昨年と今年の水量の変化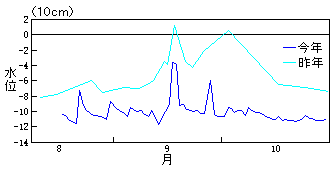 |
昨年&今年ともに9月中旬に発生量が激減した(グラフ1)理由として、同時期の水量の激増が挙げられます。グラフ7は、昨年と今年の8月~10月の水位の変化を表したものですが、明らかに9月中旬に水位が激増していることが分かります。台風などによる集中豪雨で水が濁り流れも激流となっているの時は「カゲロウ類は発生しない」という印象は受けますが、次で具体的な要因について説明します。
カゲロウ類には、河原の石や、水面に垂れ下がっている植物の葉などの上で脱皮をし羽化する性質を持っているものがいます。したがって水位が極端に増加すると、このような場所が水没してしまい羽化できません。また、水位が増加し流れも非常に速くなっている状況では、そこまでたどり着くことすら困難です。したがって、水位が極端に増加すると、発生量が激減してしまうと考えられます。
4.カゲロウ類の飛来数の変化と時間の関係について
 目的
目的

各カゲロウ類において、飛来数の時間による変化を調べ、その変化が何に関係しているのかを知る。
 まえおき
まえおき

昨年のライトトラップの結果、暗くなるにつれて飛来数が増加し、ピークに達すると極端に減少するということが分かりました。そこで今年は、調査の時間帯を「日の入りから1時間」と設定し15分ごとの飛来数の変化を調べました。
 調査方法
調査方法

調査時間を15分ごとに区切り、No.1,No.2,No.3,No.4と分けました。また、飛来数がピークに達したと思われる時間も記録しました。
 結果
結果

<グラフ9> チラカゲロウの時間別飛来数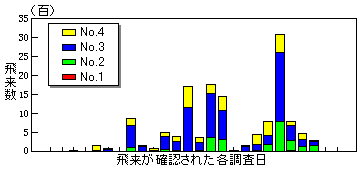 <グラフ10> エルモンヒラタカゲロウの時間別飛来数 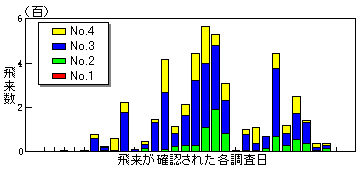 <グラフ11> キイロカワカゲロウの時間別飛来数 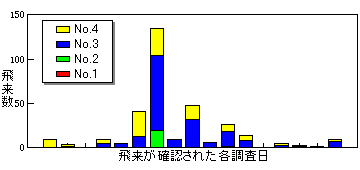 <グラフ12> ムスジモンカゲロウの時間別飛来数 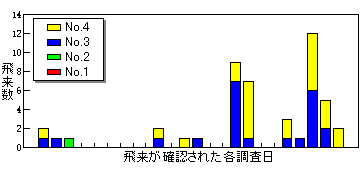 <グラフ13> ヒゲナガカワトビケラの時間別飛来数 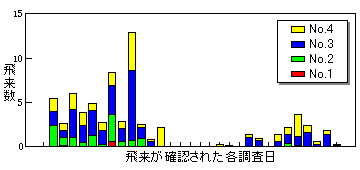 <グラフ14> 日の入りの時間と飛来数のピーク 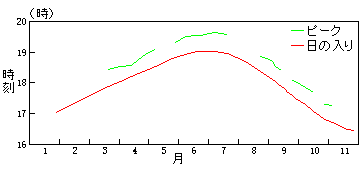 |
時刻と飛来数の関係を、グラフ9~13(調査時間を4区切りにした積み重ねグラフ)に示しました。各調査日の「日の入」の時刻をグラフ14に示しました。
グラフを見ると各調査日ともNo.3の飛来数が比較的多いことから、飛来数が最も多い時間帯は「日の入」から30~45分後であることが分かりました。また、飛来数がピークとなった時刻をグラフにプロットすると、「日の入」の時刻をなぞるような形のグラフ(グラフ14)が描けたことから、カゲロウ類が活動する時間帯は、「日の入」の時刻と同調していることが分かりました。
キイロカワカゲロウやムスジモンカゲロウについては、No.4の時間帯に飛来する割合が多いことから、チラカゲロウやエルモンヒラタカゲロウよりも活動時間が多少遅いのではないかと思われます。
 まとめ
まとめ

チラカゲロウとエルモンヒラタカゲロウについて、1日の飛来総数を100として、No.1からNo.4の割合を表したのがグラフ15,16です。
グラフを見ると、全体を通してNo.3の飛来数が多いことが分かります。また、No.4の飛来率が極端に多い日はNo.2の飛来率が少なく、No.2の飛来率が極端に多い日にはNo.4の飛来率が少なくなっていることも分かります。これは、カゲロウ類の比較的多く飛来する時間帯が、前者はNo.3からNo.4にかけて、後者はNo.2からNo.3にかけてであることを裏付けています。
<グラフ15> チラカゲロウのNo.別飛来数の割合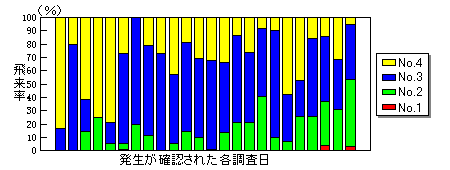 <グラフ16> エルモンヒラタカゲロウのNo.別飛来数の割合 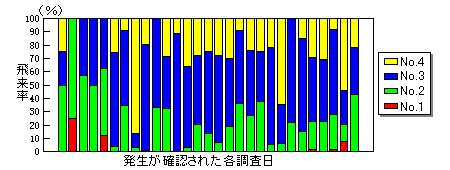 |
5.水位の変化とカゲロウ類の発生量の関係について
 目的
目的

水位の増減と発生量との関係の有無について知る。
 まえおき
まえおき

昨年の調査で、水位の変化をグラフ化して発生量の変化と比較してみました。その結果、水位の増減と発生量との間に関係があるように思えたが、はっきりとしたことはわからなかったので、今年は以下の調査により関係の有無を調べました。
 調査方法
調査方法

4月~7月は1日おき、8月~10月は毎日水位を測定しました。発生量の変化についてはライトトラップの調査結果を使用しました。
 結果・まとめ
結果・まとめ

<グラフ17> 水位変化とチラカゲロウの発生量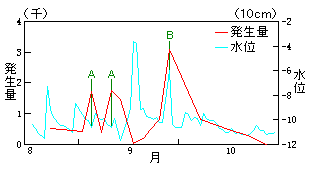 <グラフ18> 水位変化とエルモンヒラタカゲロウの発生量 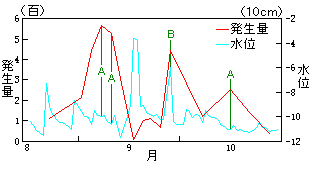 |
8月中旬~10月にかけての、水位の変化と発生状況との関係について検討しました。水位の増減と発生量との関係について、グラフ17・18に表しました。
グラフを見ると、9月17日の調査ではチラカゲロウ,エルモンヒラタカゲロウともに発生量が激減しているのが分かりますが、これについては上で説明したので省略します。
水位が減少しているときに発生量が増加しているところもありますが(グラフ中、A部)、水位が極端に増加しているにもかかわらず発生量が増加している日も見うけられます(グラフ中、B部)。この様に今回の調査からもはっきりとした結果は得られませんでした。
6.エルモンヒラタカゲロウの年2回発生について
 目的
目的

エルモンヒラタカゲロウの年2回発生を明らかにし、その調査法を確立する。
 まえおき
まえおき

昨年の結果からは、エルモンヒラタカゲロウの年2回発生を明らかにすることはできませんでした。そのため今回は、毎月1回幼虫の体長を測ることで、年2回発生を明らかにしようとしました。
 調査場所
調査場所

ライトトラップを行った場所に近い、新鬼怒橋下の河原で行いました。
 調査方法
調査方法

毎月1回、水深50cm位の場所でランダムに石を取り、そこに付着しているエルモンヒラタカゲロウの幼虫を採取し、各個体の体長を測定しました。体長の測定は1mmの目盛りまで読み取り、それよりも小さな値については四捨五入しました。
 結果の処理
結果の処理

①1月~10月の調査で採取した個体について、体長別に頭数をカウントした集計結果を表2にまとめました。
| <表2> 各月の体長別頭数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 調査日 | 体長(mm) | 合計 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 1月 | 1/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 2月 | 2/28 | 1 | 4 | 11 | 20 | 20 | 8 | 5 | 2 | 71 | ||||||||||
| 3月 | 4/3,9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 67 | ||||||
| 4月 | 4/30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||
| 5月 | 5/29 | 4 | 6 | 24 | 24 | 47 | 33 | 28 | 18 | 5 | 4 | 173 | ||||||||
| 6月 | 7/13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 32 | |||||||||
| 7月 | 8/6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 71 | |||||||
| 8月 | 9/2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| 9月 | 9/29 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 57 | |||||||
| 10月 | 10/29 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 7 | 1 | 85 | ||||||
②表2より、1月や4月,8月の採集量は他の月に比べ少なく、データとしての信頼性を欠くと判断したため、「1月+2月、3月+4月」といったように2ヶ月間のデータを1回分の結果としてまとめました。
③各調査ごとの合計にばらつきがあるため、採集された合計を100として体長別の頭数をその割合(%)として求めました(表3)。
| <表3> 各調査における体長別頭数の割合:単位(%) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 体長(mm) | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1・2月 | 1.3 | 6.6 | 15.8 | 27.6 | 27.6 | 11.8 | 6.6 | 2.6 | ||||||||||
| 3・4月 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 4.8 | 8.4 | 12.0 | 12.0 | 8.4 | 9.6 | 7.2 | 1.2 | ||||||
| 5・6月 | 2.0 | 3.9 | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 17.1 | 14.6 | 10.2 | 8.8 | 3.9 | ||||||||
| 7・8月 | 1.0 | 4.3 | 7.6 | 15.2 | 15.2 | 13.0 | 16.3 | 9.8 | 10.9 | 2.2 | 4.3 | |||||||
| 9・10月 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 12.0 | 13.4 | 15.5 | 16.2 | 14.1 | 9.2 | 7.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
④表3をもとにグラフ19を描きました。グラフの一番手前の帯は1&2月に、一番奥の帯は9&10月に採集した幼虫の体長構成を表しています。
<グラフ19> 各調査ごとの幼虫の体長構成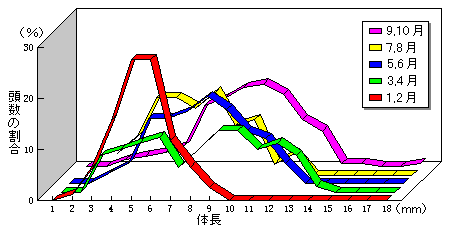 |
 結果・まとめ
結果・まとめ

各月とも体長が2mm以下のものや14mm以上のものはほとんど採取されませんでした。1&2月の帯を見ると、10mm以上のものはなく比較的中型のものが多いが、3&4月には4~7mmのものは減少し、比較的大型(10mm以上)のものが増えてきました。さらに、5&6月には3~5mmの小型のものは減少し、全体的に中~大型のものが多くなっていく様子が分かりました。9&10月には9mm以上の大型の幼虫がほとんどでした。以上のように、月を追うごとに幼虫が成長していく様子がグラフから読み取れました。
しかしながら今回の調査では「エルモンヒラタカゲロウの年2回発生を明らかにする」ところまでにはいたりませんでした。7&8月の帯を見ると、5&6月に比べ多少成長が後退しているようにも見えますが、やはりはっきりとした結果は得られませんでした。理由としてはまず、採集した幼虫が少なすぎたこと、月ごとの採集量にばらつきがあったことが考えられます。「幼虫を最低でも50頭は採集する」という目標はありましたが、実際に同定を行ってみると採集量には調査日によって大きなばらつきが生じていました。また、調査方法自体にも問題があったとも考えられます。例えば体長の小さな幼虫は、石につかまる力が弱く、石を取り上げた際の水流の変化で川中に流されやすかったとしたら、やはり調査結果に片寄りが出てきてしまうでしょう。
今回の調査では目的こそ達成できませんでしたが、今後の調査を行う上でのよい資料を得ることができました。
7.鬼怒川上流域における幼虫の生息調査報告
 目的
目的

水生昆虫の生態についてより深い理解を得るため、幼虫期の生態についても詳しく知る必要があると考え、以下に示す2点を目的としました。
・定量的調査法を試行することにより、幼虫の採集方法や生活環境について知る。
・鬼怒川に生息している幼虫の種・数・生息地域などを調べ、幼虫の生息分布について知る。
 まえおき
まえおき

昨年度我々は上で述べた目的をふまえ、鬼怒川上・中流域において幼虫の生息調査を実施しました。今年は昨年度対象とした調査範囲よりも更に上流域において幼虫を採集することができましたので、その結果を報告します。
 調査場所
調査場所

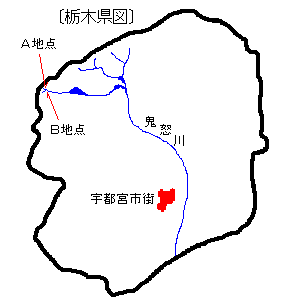 |
昨年は鬼怒川の上流、栗山村の女夫淵温泉付近を最上流部の調査地点としたが、今年は更に上流に3km程さかのぼった日光沢温泉(A地点)と加仁湯温泉(B地点)付近の2ヶ所の流れにおいて調査を行いました。
 調査方法
調査方法

各調査地点において河原に近い流れの緩やかなところと、川の中心付近の比較的流れの速いところの2ヶ所でコドラート法を行いました。
※コドラート法については平成6年度調査報告を参照してください。
 結果
結果

 調査時のデータ
調査時のデータ
各調査地点のデータは以下の通りです。
| <A地点> | <B地点> | |
|---|---|---|
| 日時 | 8/25PM4:00頃 | 8/25PM5:00頃 |
| 天候 | 晴れ | 晴れ |
| 気温 | 25.0℃ | 21.6℃ |
| 水温 | 16.8℃ | 16.2℃ |
| 川幅 | 約15m | 約4m |
| 河原の幅 | 約30m | 約30m |
 同定結果
同定結果
計81頭の幼虫を採取しました(表4)。採集された幼虫は、カゲロウ目、カワゲラ目、トビケラ目、双翅目のいずれかに属しました。これは昨年度の調査結果と同じですが、昨年度採集された双翅目(21頭)は全てさなぎであったのに対し、今回採集されたものは2頭とも幼虫でした。
また、昨年度の調査ではエルモンヒラタカゲロウ、シロタニガワカゲロウ、ヒゲナガカワトビケラの確認数が特に多かったですが、今回の調査ではヒゲナガカワトビケラ1頭を確認するにとどまりました。それに対し、昨年度1頭しか確認することができなかったユミモンヒラタカゲロウを今年は9頭確認することができたことから、本種は河川の上流域において生息している種だということが裏付けられました。
| カゲロウ目 | A地点 | B地点 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヒラタカゲロウ科 | ヒラタカゲロウ属 | ユミモンヒラタカゲロウ | 8 | 1 | 9 |
| ナミヒラタカゲロウ | 5 | 4 | 9 | ||
| タニヒラタカゲロウ | 2 | 2 | |||
| ヒメヒラタカゲロウ属 | ミナズキヒメヒラタカゲロウ | 1 | 1 | ||
| オビカゲロウ属 | オビカゲロウ | 1 | 1 | ||
| マダラカゲロウ科 | マダラカゲロウ属 | ヨシノマダラカゲロウ | 1 | 1 | 2 |
| オオクママダラカゲロウ | 1 | 1 | |||
| 種不明 | 2 | 2 | |||
| コカゲロウ科 | コカゲロウ属 | フタバコカゲロウ | 1 | 1 | |
| 種不明 | 8 | 7 | 15 | ||
| 属不明 | 5 | 2 | 7 | ||
| フタオカゲロウ科 | フタオカゲロウ属 | ヒメフタオカゲロウ | 1 | 1 | |
| 属不明 | 2 | 2 | |||
| 科不明 | 1 | 1 | |||
| カワゲラ目 | A地点 | B地点 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カワゲラ科 | オオヤマカワゲラ属 | オオヤマカワゲラ | 1 | 1 | |
| ヒメオオヤマカワゲラ | 2 | 2 | |||
| 種不明 | 1 | 1 | |||
| クラカケカワゲラ属 | 種不明 | 1 | 1 | ||
| カミムラカワゲラ属 | 種不明 | 1 | 1 | ||
| 科不明 | 1 | 4 | 5 | ||
| トビケラ目 | A地点 | B地点 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| ヒゲナガカワトビケラ科 | ヒゲナガカワトビケラ | 1 | 1 | |
| シマトビケラ科 | ウルマーシマトビケラ | 1 | 8 | 9 |
| ナガレトビケラ科 | 種不明 | 3 | 1 | 4 |
| 双翅目 | A地点 | B地点 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| アミカ科 | 属不明 | 2 | 2 | |
8.おわりに
昨年昆虫班から分離し、新制ベントス班として「カゲロウの生態」というテーマについて研究することにした。アミメカゲロウだけにこだわらず鬼怒川に生息しているカゲロウやトビケラなどの水生昆虫を対象に、その生息分布や生活形態について調査を行った。そういった中でまず最初に行った調査がライトトラップによる年間を通してのカゲロウ類の発生状況についてである。今年も昨年と同様に発生状況についての調査をメインに行ったのだが、今年は昨年の調査結果から生じた問題点のいくつかについて、調査方法に改善を加え更に踏み込んだ調査を行った。調査方法については年間計画を立てる段階でいろいろと話し合ったのだが、結局「これだ」といったような調査方法は思い浮かばず、「とりあえずやってみよう」といった気持ちで調査に乗り出した。
今年のベントス班の調査は年間を通してコンスタントに行うものがほとんどであったため、調査期間が非常に長く、班員にとっては気の抜けない状態が長く続き負担となった。また、夏休みには班員の予定がかみ合わなかったため、調査日の間隔がまちまちになってしまい、「年間を通して」のデータに穴が空いてしまう結果となった。しかしながら9月に入ると、テスト期間であったにもかかわらず班員の積極的な調査への参加が見られたことにより、データとしても濃いものが得られ、班員同士の団結にもつながったと感じている。また、今年初めて行った調査もあり、これについてはやはり手探り状態とも言える調査となってしまった。調査を行う前の下調べや予備調査を行うことの大切さを痛感した。
夏休みにはサンショウウオ班と合同で奥鬼怒(鬼怒沼)において合宿を行った。単調でマンネリ気味であった普段の調査とは違った新鮮さを感じることができ、班員にとってもよい息抜きになった。また、昨年行った幼虫の生息調査における調査地点よりも更に上流部で幼虫を採集することができ、昨年のデータに付け足すことにより、データの蓄積につながった。
今年のカゲロウ類の発生量は昨年の3分の1程度であったため、同定作業も速やかに終わらす事ができ、班員の労力も軽減した。その結果、調査結果の処理に時間を費やすことができ、様々な考察について話し合えたことはよかった。1年生もカゲロウ類に興味を持ってくれたようで、来年の調査に向けての足がかりになったと思う。
最後に、ライトトラップの調査道具一式を提供してくださった生物研究会顧問の中村先生を始め、調査に協力してくれた会員の皆さんに感謝の意を表し終わりとする。