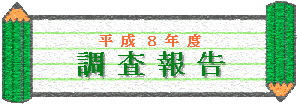
1.はじめに
カゲロウの生態について以下に示す2つのテーマを定め、鬼怒川において調査しました。
①鬼怒川中流域における発生状況について
②カゲロウの羽化後から死ぬまでの期間について
2.カゲロウ類の紹介
 アミメカゲロウ(蜉蝣目アミメカゲロウ科アミメカゲロウ属)
アミメカゲロウ(蜉蝣目アミメカゲロウ科アミメカゲロウ属)
9月の中旬に集中して羽化する年1回発生。日本各地で発生の記録はあるが、阿武隈川(福島県)、那珂川(茨城県)を除く各地で発生するのは雌のみ。
【 成虫の特徴 】
体長9mm前後。尾は雄が2本、雌が3本。全体に白っぽく、肢が貧弱で体を支えることができない。
【 幼虫の特徴 】
体長12mm前後。大型のもので20mm。掘潜型で、早瀬の石の下の安定した砂泥中に巣穴を掘って生息。
 チラカゲロウ(蜉蝣目チラカゲロウ科チラカゲロウ属)
チラカゲロウ(蜉蝣目チラカゲロウ科チラカゲロウ属)
5~6月、9~10月に羽化する年2回発生。山地渓流から平地の流れにかけて広く見られる。本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長16~18mm。尾は2本。頭部は光沢のある黒色、胸部と腹部は濃い褐色。
【 幼虫の特徴 】
体長18mm位。尾は3本。全体が黒褐色で、水中を自由に泳げる円筒形。
 エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
晩春から初夏、初秋から晩秋にかけて羽化する年2回発生。羽化直前になると川底から離れ、水面に浮かび出てくると背中が裂けてパッと羽化する。山地渓流から平地の流れにかけて広範囲に見られる。北海道・本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長9~10mm。尾は2本。全体が薄黄色をおび、翅の付け根にL(エル)の紋がある。
【 幼虫の特徴 】
体長10~15mm。尾は2本。偏平な形で、川底の石について生息。鰓の半分以上に大小赤紫の点紋が散在。
 キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
6~8月に羽化する年1回発生。北海道・本州・四国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長10~11mm。尾は3本。全体が黄色をおび、翅は無色透明だが、前翅の前縁に褐色の部分がある。
【 幼虫の特徴 】
体長8~10mm。尾は3本。全体が淡黄褐色で、緑褐色の斑紋があり、体型は細長くやや円筒形。低山地や平地の流水の緩やかな部分の石の下に生息。
 ムスジモンカゲロウ(蜉蝣目モンカゲロウ科モンカゲロウ属)
ムスジモンカゲロウ(蜉蝣目モンカゲロウ科モンカゲロウ属)
4~5月、8~9月に羽化する。本州・四国・中国・九州に分布。
【 成虫の特徴 】
体長13~17mm。尾は3本。全体が黄白色をおび、腹節には2~3対の黒色の縦状紋がある。羽は無色透明で、前翅中央に黒褐色の斑紋がある。
【 幼虫の特徴 】
体長20mm。尾は3本。腹部背面に斑紋が3対縦状にある。平地の流水及び浅い湖沼の砂泥低に埋もれて生息。
 ヒゲナガカワトビケラ(毛翅目ヒゲナガカワトビケラ科)
ヒゲナガカワトビケラ(毛翅目ヒゲナガカワトビケラ科)
4月末~10月末に羽化し、河川の上流から下流まで広く生息する。北海道・本州・四国・九州に分布する。
【 成虫の特徴 】
体長約20mm。尾はない。頭胸部、前翅は暗褐色である。触覚が前翅長より長いので(時に雄は1.5倍ある)この名がついた。
【 幼虫の特徴 】
体長30~40mm。全体が黒褐色で光沢があり、体型は長い円柱状である。礫底の川に生息し、礫の裏側に口から糸を出して網を張り、固着巣を作成する。
3.鬼怒川中流域におけるカゲロウ類の発生状況について
 目的
目的

年間を通してカゲロウ類の発生状況を把握し、昨年、一昨年の発生状況と比較する。
 調査状況
調査状況

栃木県宇都宮市石井町の新鬼怒橋下(鬼怒川石井水位観測所付近)の河原において調査を行いました(図1、図2)。
<図1> 調査場所の位置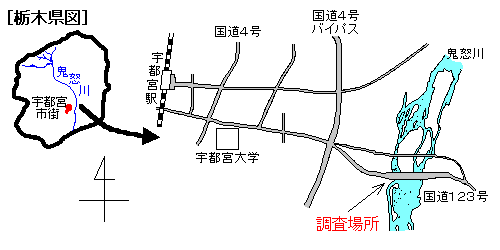 |
<図2> 調査場所の様子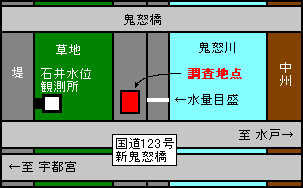 |
 調査時期
調査時期

カゲロウ類が発生し始める4月~10月にかけて、1週間に1度、日没から1時間調査を行いました。
 調査方法
調査方法

<図3> ライトトラップの装置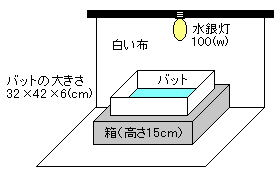 |
調査はライトトラップ(過去の調査報告を参照してください)により行いました。調査時間は、日の入り5分前に水銀灯をつけ、日の入りから1時間調査を行いました。調査時には気温・水温・水位を測定しました。
 結果
結果

| <表1>各調査日のデータ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 日の入り | 水温(℃) | 気温(℃) | 水位 | 天気 |
| 4/1 | 18:03 | 8.2 | 6.0 | -8.3 | 曇り |
| 4/13 | 18:17 | 10.5 | 8.1 | -12.0 | 晴れ |
| 4/20 | 18:19 | 10.8 | 9.8 | -11.3 | 晴れ |
| 4/30 | 18:29 | 15.1 | 16.0 | -11.2 | 曇り |
| 5/4 | 18:30 | 15.0 | 19.0 | -11.7 | 晴れ |
| 5/13 | 18:39 | 13.2 | 10.5 | -9.0 | 晴れ |
| 5/19 | 18:44 | 16.1 | 14.8 | -10.2 | 晴れ |
| 5/28 | 18:50 | 18.3 | 22.5 | -10.5 | 晴れ |
| 6/1 | 18:53 | 17.1 | 14.5 | -10.5 | 曇り |
| 6/11 | 19:05 | 17.0 | 20.5 | -11.0 | 曇り |
| 6/17 | 19:02 | 19.0 | 21.0 | -11.0 | 曇り |
| 6/27 | 19:00 | 17.0 | 20.0 | -11.0 | 曇り |
| 7/6 | 19:00 | 21.0 | 24.2 | -11.5 | 晴れ |
| 7/21 | 18:57 | 21.0 | -12.2 | 晴れ | |
| 7/23 | 18:57 | 19.0 | 20.5 | -10.5 | 曇り |
| 7/28 | 18:53 | 22.0 | 21.0 | -11.5 | 曇り |
| 8/4 | 18:44 | -11.8 | 曇り | ||
| 8/11 | 18:36 | 晴れ | |||
| 8/18 | 18:28 | -12.0 | 曇り | ||
| 8/25 | 18:19 | -11.5 | 晴れ | ||
| 9/2 | 18:08 | -12.0 | 曇り | ||
| 9/8 | 17:59 | 22.0 | 22.0 | -11.0 | 晴れ |
| 9/15 | 17:48 | 20.0 | 22.0 | -11.0 | 曇り |
| 9/27 | 17:30 | 07.9 | 15.9 | -10.0 | 曇り |
| 10/5 | 17:19 | 19.5 | 19.0 | -10.0 | 晴れ |
| 10/12 | 17:09 | 17.0 | 17.5 | -11.0 | 曇り |
| 10/21 | 16:57 | 16.0 | 11.5 | -11.0 | 晴れ |
| 10/26 | 16:51 | 16.0 | 16.0 | -11.5 | 曇り |
4月~10月までに、計26回調査を行いました。次で、昨年と一昨年の発生量についてもあわせて比較しました。結果の比較はカゲロウ類の確認できた4月からデータ整理のできる10月までとしました。
 チラカゲロウ(確認数:3339頭)
チラカゲロウ(確認数:3339頭)
<グラフ1> H8年度チラカゲロウの発生状況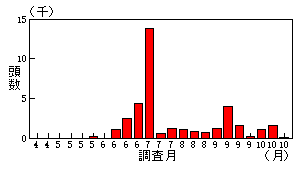 |
調査対象としたカゲロウの中で最も多く飛来し、これは3年間同じ結果でした。年2回発生といわれていますが、その様子がグラフに現れていました。平成6年8月~9月にかけての大量発生は平成7年、8年には見られませんでした。
 エルモンヒラタカゲロウ(確認数:2429頭)
エルモンヒラタカゲロウ(確認数:2429頭)
<グラフ2> H8年度エルモンヒラタカゲロウの発生状況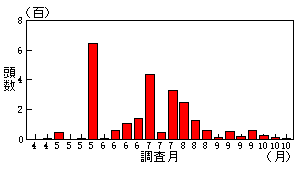 |
年2回発生のカゲロウと言われていますが、今年もはっきりとした特徴が分からない結果となりました。発生時期は3年間共通していました。
 キイロカワカゲロウ(確認数:628頭)
キイロカワカゲロウ(確認数:628頭)
<グラフ3> H8年度キイロカワカゲロウの発生状況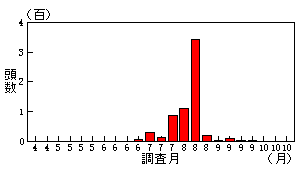 |
年1回発生のカゲロウと言われている通り、グラフを見ると8月をピークとして発生していました。
 ムスジモンカゲロウ(確認数:93頭)
ムスジモンカゲロウ(確認数:93頭)
<グラフ4> H8年度ムスジモンカゲロウの発生状況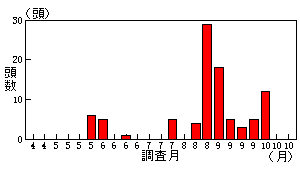 |
4月~5月、8月~9月の年2回発生といわれていますが、8月~10月に多く発生し、4月~5月には発生していない結果となりました。
 ヒゲナガカワトビケラ(確認数:1811頭)
ヒゲナガカワトビケラ(確認数:1811頭)
<グラフ5> H8年度ヒゲナガカワトビケラの発生状況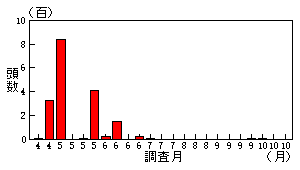 |
4月~10月にかけて発生すると言われていますが、4月~6月にかけて集中的に発生していました。
 アミメカゲロウ(採取数:0頭)
アミメカゲロウ(採取数:0頭)
一昨年は9頭確認することができましたが、今年は昨年と同様確認できませんでした。
 カゲロウ類の総数(確認数:計6807頭)
カゲロウ類の総数(確認数:計6807頭)
<グラフ6> H8年度カゲロウ類の発生状況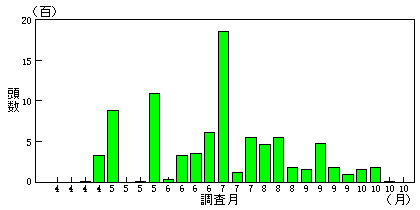 <グラフ7> H7年度カゲロウ類の発生状況 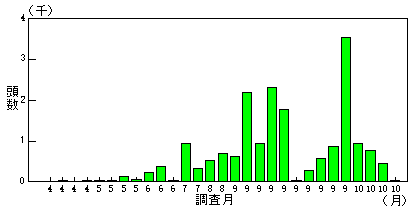 <グラフ8> H6年度カゲロウ類の発生状況 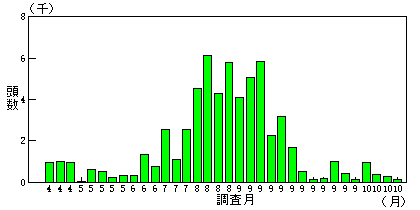 |
平成6年8月の大量発生は先に述べたチラカゲロウの大量発生が原因と思われます。カゲロウ類の発生時期は3年間共通して4月~10月にかけて起こっていました。
 まとめ
まとめ

<グラフ9> 3年間の雌雄の比率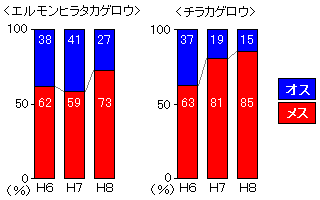 <グラフ10> 3年間の水位の変化 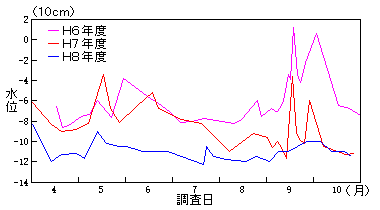 |
水銀灯に飛来したエルモンヒラタカゲロウとチラカゲロウの雌雄の比率をグラフ9に示しました。羽化時の雌雄の比率は分かりませんが、水銀灯への飛来頭数は3年間共通してメスが多くなりました。
3年間の水位の変動をグラフ10に示しました。3年間の調査の結果、カゲロウの確認数が減少していました。そこで、水位の変動に注目すると、平成6年から平成8年にかけて水位が下がっていることがわかります。このことが確認数の変化と関連があるとは言えませんが、調査期間に気づいた環境の変化として挙げます。
しかしながら、カゲロウ類の全体数が年々減少しているとは考えられません。というのは、3年間各年ごとに調査回数が異なったり、カゲロウ類が時期によって発生頭数に差のある生物であるため、1週間に1度の調査では発生数を確実に把握することが困難だからです。具体的に述べると、平成6年、平成7年には9月のみ3日に1度のペースで調査をしましたが、平成8年は1週間に1度のペースで調査をしました。このことで確認数に差が出てくるのは当然です。また、発生数の多い時期に調査をしたかどうかによっても確認数に差が出てきます。このような理由により、今回の結果のみでカゲロウ類の増減を考察するのは難しと考えます。
4.カゲロウの羽化から死ぬまでの期間について
 目的
目的

カゲロウの幼虫を人工的な環境で羽化させ、羽化後の寿命を確認する。
 調査の動機
調査の動機

同定能力向上のために人工的な環境でカゲロウを羽化させたい、カゲロウの羽化後の寿命が文献により異なっているため実際に調べてみたいと思ったことが動機で今回の調査を計画しました。
 調査方法
調査方法

室内に循環式の水槽を置き、採取してきたカゲロウの幼虫を放し、水槽内で生きることができるか、羽化できるか、羽化後どの位生きるかについて観察しました。
 水槽について
水槽について
<図4> 水槽の図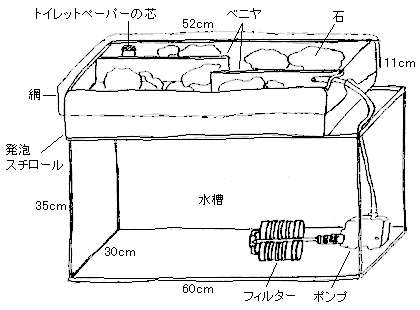 |
水槽部よりポンプで水をくみ上げ、発泡スチロール部に流します。発泡スチロールの中はベニヤ板で区切って水路を作り、一定の水位を保てるようにしました。また、中に川より取ってきた砂利や石を置き(石に付いている藻が餌となるようにするため)、自然の川に近い環境にしました。さらに、水の出口に網を張り、幼虫や幼虫の死骸などが水槽部に落ちるのを防ぎました。水は地下水を利用し、ポンプの吸水口にフィルターを付け、5日に1度水を交換しました。発泡スチロール部は網で覆い、羽化したカゲロウが逃げるのを防ぎました。
 幼虫の採取について
幼虫の採取について
<図5> カゲロウの採取場所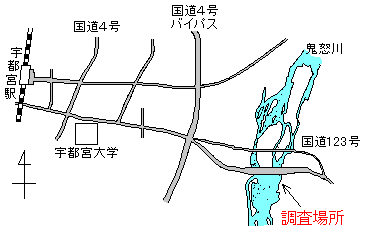 |
幼虫は栃木県宇都宮市石井町の新鬼怒橋下の河原で、8月24日に採取しました。水深50cm程度の水底よりランダムに石を取り、そこに付着している幼虫を採取し、その日のうちに発泡スチロール部に放しました。
 幼虫の観察について
幼虫の観察について
<図6> 部室内の水槽の位置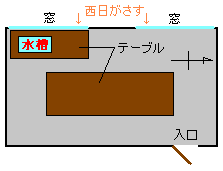 |
幼虫の観察時間帯は夕方から夜にし、毎日必ず1回は観察しました。同時に羽化後の様子についても観察しました。
 羽化後のカゲロウの観察について
羽化後のカゲロウの観察について
<図7> 三角コーナー用のごみ袋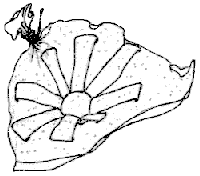 |
羽化を確認したら、1頭ずつ確認日と時間を記入し、穴の開いた三角コーナー用のビニール袋に入れ、観察しました。確認できるときは、亜成虫から成虫までの期間ついても確認しました。なお、袋の中には紙コップをプロペラ状に広げたものを入れ、空間を保てるようにしました。
 結果
結果

観察時の気温、水温を表2に示しました。循環式水槽内は、水温調節を怠ったため実際の川の水温より高くなることがありました。
| <表2> 気温と水温 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 時刻 | 気温 | 水温 | 調査日 | 時刻 | 気温 | 水温 | 調査日 | 時刻 | 気温 | 水温 |
| 8/25 | 22:00 | 23.5 | 24.0 | 8/28 | 21:35 | 18.0 | 20.5 | 8/31 | 23:53 | 25.8 | 25.8 |
| 8/26 | 21:30 | _ | _ | 23:50 | 20.0 | 21.5 | 9/4 | 18:30 | _ | 25.5 | |
| 8/27 | 13:00 | 23:50 | 20.0 | 8/29 | 13:20 | 20.0 | 22.3 | 9/5 | 20:30 | 25.0 | 25.5 |
| 21:00 | 21.0 | 23.0 | 20:00 | 22.5 | 23.0 | 9/6 | 18:40 | 25.0 | 26.0 | ||
| 23:45 | 21.0 | 23.0 | 8/30 | 13:00 | 26.0 | 24.0 | 9/8 | 19:30 | 25.0 | 22.0 | |
| 8/28 | 16:20 | 20.0 | 22.0 | 22:15 | 24.5 | 24.5 | |||||
8月24日に幼虫を約80頭採取し、9月8日まで観察を続けました。種類にはこだわらず、なるべく大きな個体を選び採取しました。これらのうち25頭について羽化・脱皮・死亡の日時が確認できたので個体別に表3にまとめました。他に、羽化日のみ確認できた個体が4頭、亜成虫の状態で死亡した個体が22頭、成虫の状態で死亡した個体が1頭いました。以上より、羽化が確認できた個体は52頭となり、採取してきた幼虫の約6割という結果となりました。なお、確認はできませんでしたが、幼虫の殻から他にも羽化した個体がいたことがうかがえました。以上より、多少の流れのあるところでカゲロウを羽化させることができることが分かりました。
次に羽化後の寿命についてですが、亜成虫から成虫に脱皮する期間が1日~2日かかる事が分かりました。脱皮後はB,Cのように3日生きるものもいれば、A,Dのように6日生きるものもおり、ばらつきのある結果となりました。このことから今回設定した環境では亜成虫・成虫期間を合わせて約1週間生きることが分かりました。
<表3> 羽化後の生存期間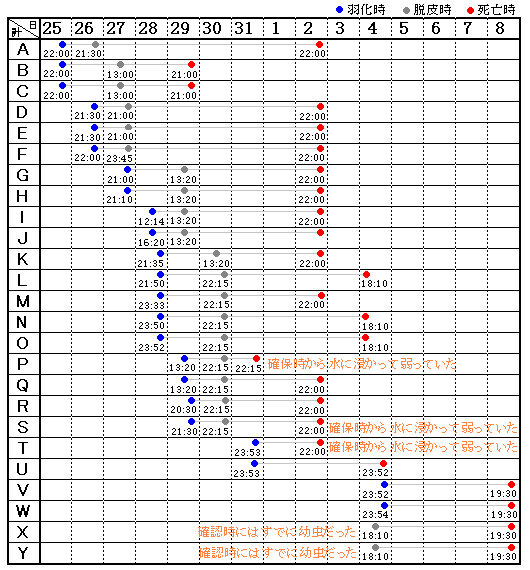 |
 まとめ
まとめ

80頭中、水槽内で羽化した個体が52頭で、人工的な環境で羽化させることは成功したと思いますが、実際にデータの取れたものは25頭のみでした。理由として、亜成虫が22頭死亡していることから、発泡スチロール部の網の高さが不十分で飛行空間が狭かったこと、羽化をするための陸地となる部分が狭かったこと、観察をもっと密に行わなかったことが挙げられます。また、発泡スチロールと網との隙間を減らす工夫が必要でたっだと思います。
5.おわりに
昨年、一昨年に続きライトトラップは今年で3度目となった。コンスタントに続く調査のためか、1週間に1度のペースを保つために班員全員の協力が必要となり、気が抜けない8ヶ月だった。残念だったことは、班員の予定や悪天候のために1週間に1度のペースを守れないことが2度ほどあったことだが、今は3年分のデータが取れてほっとしている。
夏休みに行ったカゲロウの羽化から死ぬまでの期間の観察は初めての試みで本当に調査ができるのか不安だった。予備調査をしたにもかかわらず、羽化した亜成虫や成虫を逃がしたり、死なせたりと悔いが残った。また、調査にとりかかるのが遅かったため、調査に十分な時間をかけることができず残念だった。しかし、一応目的を達成することができ、嬉しく思うのと同時に、この調査が今後の調査に何らかの役に立てばと思う。
最後に、ライトトラップの調査道具一式を提供してくださった生物研究会顧問の中村先生、OBの蓮田さん、調査に協力してくれた会員の皆さんに感謝の意を表し終わりとする。