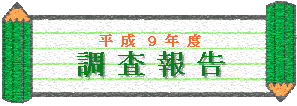
1.はじめに
「カゲロウの羽化から死ぬまでの期間について」というテーマを定め、調査・観察しました。
2.カゲロウ類の紹介
今年は昨年までとは趣向を変え、幼虫をメインに調査を行ったので幼虫の絵を添えることにしました。カゲロウの幼虫は植物性の食物(硅藻のような水中の石についた微小藻類)を食べています。データが取れたカゲロウ(エルモンヒラタカゲロウ、キイロカワカゲロウ、シロタニガワカゲロウ)の3種について紹介します。
 エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
エルモンヒラタカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科ヒラタカゲロウ属)
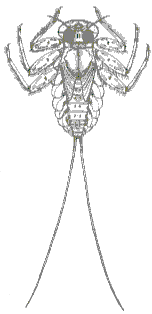 |
成虫は体長9~10mm、尾は2本ある。全体が薄黄色をおび、翅の付け根にL(エル)の紋がある。晩春から初夏、初秋から晩秋にかけて羽化する年2回発生である。幼虫は偏平な形で、体長は10~15mm、川底の石について生息し、大小の赤紫褐色の点紋が、鰓の半分以上に散在している。羽化直前になると川底から離れ、水面に浮かび出てくると背中がパッと羽化する。山地渓流から平地の流れの激しい区域の石面に付着して生活し広範に見られる。
 キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
キイロカワカゲロウ(蜉蝣目カワカゲロウ科カワカゲロウ属)
 |
成虫は体長10~11mm、尾は3本ある。全体が黄色をおび、翅は無色透明だが、前翅の前縁に褐色の部分がある。初夏から中夏に羽化する年1回発生である。幼虫は体長8~10mm、全体が淡黄褐色で緑褐色の斑紋があり、体型は細長くやや円筒形である。低山地や平地の流水のゆるやかな所の石の下に生息する。北海道・本州・四国・九州に分布する。
 シロタニガワカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科タニガワカゲロウ属)
シロタニガワカゲロウ(蜉蝣目ヒラタカゲロウ科タニガワカゲロウ属)
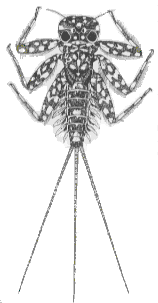 |
幼虫は体長10~12mm、尾は3本ある。体は偏平で暗緑黄色であり、尾の長さは体長より長い。頭部は大きく、前縁に4個の淡色の小円斑がある。河川の流れが急な区域の石礫下に生活し、また湖沼の石礫湖岸にもいる。5~6月頃羽化する。
3.カゲロウの羽化から死ぬまでの期間について
 目的
目的

カゲロウの幼虫を人工的な環境で羽化させ、寿命の期間を認識する。
 調査の動機
調査の動機

昨年の実験では確かな結果が出なかったので、今年は調査期間を長くし、より多くのデータを得たいと考えました。
 調査方法
調査方法

 水槽について
水槽について
<図1> 水槽の図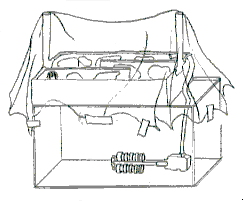 <図2> 部室内の水槽の位置 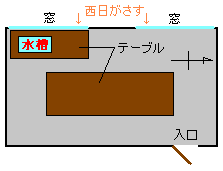 |
下の水槽よりポンプで水をくみ上げ発泡スチロール部に流します。発泡スチロール部の中はベニヤ板で区切って水路を作り、一定の水位を保てるようにした中で観察しました。
中には川より取ってきた石を置き(石に付いている藻が餌となるため)、自然の川に近い環境にしました。また、水の出口に網を張り、幼虫や幼虫の死骸などが下の水槽に落ちるのを防ぎました。水は地下水を利用し、ポンプの給水口にフィルターを付けました。生活空間を大きく保つため、発泡スチロール部の上にポールを立て、その上に網をはりました。
 幼虫の採取について
幼虫の採取について
<図3> カゲロウの採取場所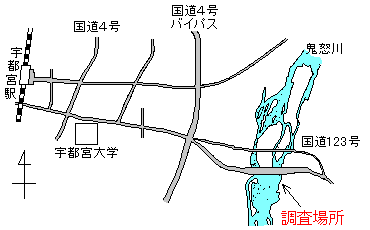 |
栃木県宇都宮市石井町の新鬼怒橋下の河原で採取しました。水底よりランダムに石を取り、そこに付着している幼虫を採取し、その日のうちに発泡スチロール部の中に放しました。
 幼虫の観察について
幼虫の観察について
気がついたときには何度も水槽を見て、気温・水温を計りました。同時に羽化後の様子も観察しました。
 羽化後のカゲロウの観察について
羽化後のカゲロウの観察について
<図4> 三角コーナー用のごみ袋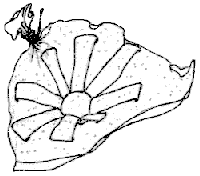 <図5> 変更した容器 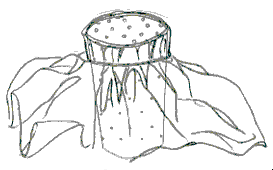 |
羽化したカゲロウは1頭ずつ確認日時を記入して、穴の開いた三角コーナー用ビニール袋に入れ、亜成虫~成虫~死の日時を確認しました。なお、ビニール袋の中には、紙コップをプロペラ状に広げたものを入れ空間を保ちましたが、圧死する個体がいたため、後半は図5の様な容器に変更しました。
 結果
結果

| <表1> | ||||
|---|---|---|---|---|
| 採取日 | 採取した数 (頭) | 羽化した数 (頭) | 水死した数 (頭) | 羽化率 (%) |
| 7/5 | 68 | 16 | 13 | 24 |
| 7/9 | ||||
| 8/14 | 51 | 29 | 3 | 57 |
| 9/6 | 89 | 11 | 3 | 12 |
| 10/22 | 72 | 4 | 2 | 6 |
5/14、7/5・9、9/6、10/22の5回で、280頭の幼虫を採取し観察を続けました。幼虫はエルモンヒラタカゲロウ、キイロカワカゲロウを多く採取するようにし、なるべく大きな個体を選びました。このうち60頭の幼虫について羽化、死亡の日時が確認できました。
採取したカゲロウ数と羽化数、羽化したが水路内で死亡た数を、採取した日にち別に表1にまとめました。また、60頭のカゲロウの羽化、脱皮、死亡の確認日を個体別に表2にまとめました。
<表2>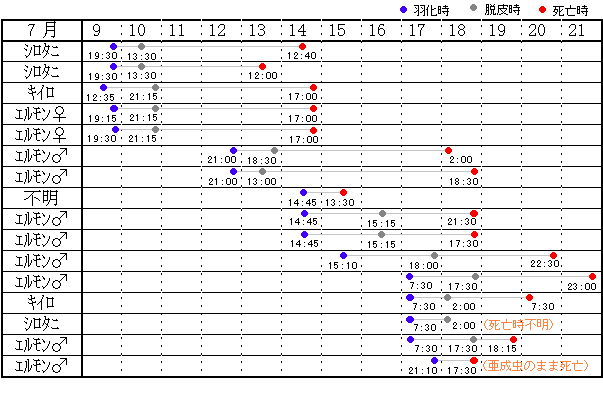 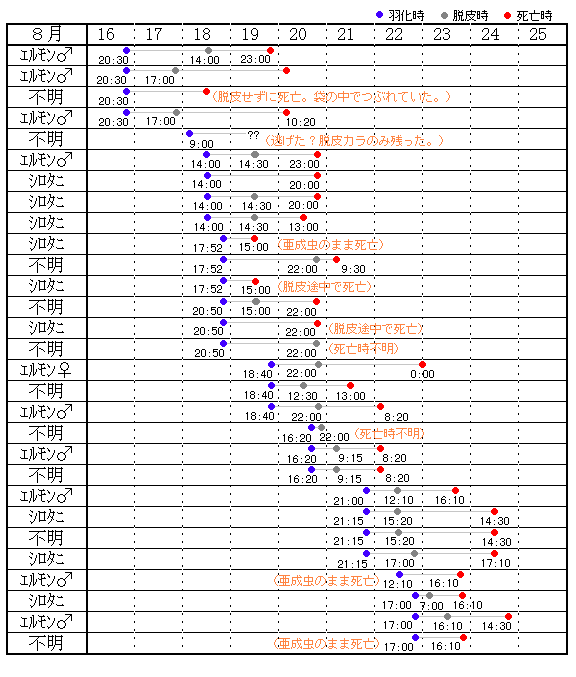 ※8/21・22日の9:00~17:00、停電のためポンプ停止 ※8/28午後、ポンプ停止(原因不明) 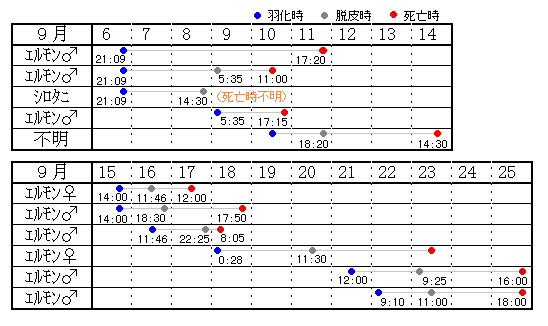
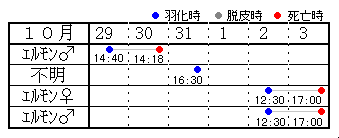 |
観察時の気温、水温などを下に示しました。
| 日付 | 時間 | 気温(℃) | 水温(℃) | 天候 | 日付 | 時間 | 気温(℃) | 水温(℃) | 天候 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日 | 5:30 | 25.0 | 22.0 | 晴れ | 8月26日 | 0:13 | 23.5 | 25.0 | 晴れ |
| 7月7日 | 12:52 | 27.9 | 23.0 | 晴れ | 15:00 | 22.0 | 26.0 | 雨 | |
| 17:40 | 32.8 | 27.0 | 晴れ | 8月27日 | 12:15 | 24.5 | 23.0 | 晴れ | |
| 21:04 | 29.0 | 24.0 | 晴れ | 24.0 | 24.5 | 晴れ | |||
| 7月8日 | 17:00 | 30.0 | 30.0 | 晴れ | 25.5 | 25.0 | 晴れ | ||
| 21:00 | 27.0 | 29.0 | 晴れ | 9月11日 | 15:30 | 26.5 | 26.0 | 晴れ | |
| 7月9日 | 9:00 | 25.0 | 26.0 | 22:30 | 24.0 | 晴れ | |||
| 10:30 | 25.0 | 25.0 | 9月13日 | 12:00 | 24.5 | 24.0 | 曇り | ||
| 7月10日 | 16:00 | 25.0 | 25.0 | 12:34 | 21.0 | 23.0 | 曇り | ||
| 21:00 | 23.0 | 26.0 | 9月14日 | 12:22 | 22.0 | 22.0 | 曇り | ||
| 7月11日 | 16:30 | 23.0 | 26.0 | 9月15日 | 14:00 | 19.5 | 21.0 | 雨 | |
| 7月13日 | 13:00 | 24.0 | 26.0 | 9月16日 | 11:46 | 18.5 | 19.5 | 曇り | |
| 7月16日 | 16:50 | 29.0 | 29.0 | 9月17日 | 18:43 | 23.0 | 23.0 | 曇り | |
| 21:14 | 26.0 | 27.0 | 9月18日 | 23.5 | 24.5 | 晴れ | |||
| 8月14日 | 18:18 | 22.5 | 19.0 | 曇り | 9月19日 | 12:30 | 23.5 | 23.5 | 晴れ |
| 8月15日 | 21.8 | 19.8 | 曇り | 9月21日 | 12:00 | 19.5 | 20.5 | 小雨 | |
| 8月16日 | 20:30 | 20.0 | 21.5 | 曇り | 9月22日 | 12:19 | 20.5 | 21.5 | 曇り |
| 8月18日 | 17:00 | 21.5 | 22.0 | 9月27日 | 16:00 | 21.0 | 22.0 | 晴れ | |
| 8月18日 | 9:00 | 23.0 | 23.0 | 晴れ | 10月23日 | 16:34 | 18.0 | 20.5 | 晴れ |
| 14:00 | 23.5 | 23.0 | 曇り | 21:00 | 21.0 | 21.5 | 晴れ | ||
| 17:52 | 24.0 | 24.0 | 曇り | 10月24日 | 11:09 | 18.5 | 16.5 | 晴れ | |
| 20:50 | 23.0 | 25.0 | 雨 | 10月25日 | 9:00 | 19.0 | 20.0 | 晴れ | |
| 8月19日 | 6:40 | 23.0 | 25.0 | 晴れ | 21:20 | 20.5 | 21.5 | 晴れ | |
| 15:15 | 25.5 | 26.5 | 晴れ | 10月26日 | 15:30 | 18.0 | 18.5 | 晴れ | |
| 21:00 | 25.5 | 26.5 | 晴れ | 10月27日 | 13:00 | 15.5 | 14.5 | 晴れ | |
| 8月20日 | 9:50 | 23.5 | 26.0 | 晴れ | 10月28日 | 12:13 | 11.0 | 15.0 | 晴れ |
| 16:20 | 25.0 | 26.0 | 晴れ | 17:40 | 15.0 | 晴れ | |||
| 20:30 | 27.0 | 23.0 | 晴れ | 10月29日 | 11:19 | 17.0 | 曇り | ||
| 8月21日 | 17:46 | 25.0 | 27.0 | 晴れ | 14:40 | 17.0 | 16.5 | 晴れ | |
| 21:00 | 26.0 | 27.0 | 晴れ | 17:00 | 20.0 | 18.0 | |||
| 8月22日 | 17:50 | 25.0 | 28.5 | 晴れ | 10月30日 | 10:30 | 17.0 | 19.0 | 晴れ |
| 8月23日 | 0:20 | 26.0 | 28.0 | 晴れ | 14:45 | 21.0 | 19.5 | 晴れ | |
| 13:30 | 26.5 | 28.0 | 晴れ | 10月31日 | 16:30 | 20.0 | 18.5 | 曇り | |
| 8月24日 | 21:00 | 24.5 | 27.0 | 晴れ | 11月2日 | 12:30 | 11.0 | 11.5 | 晴れ |
 まとめ
まとめ

ほとんどの幼虫は羽化後1~2日で脱皮し、成虫になるということがわかりました。脱皮後の寿命は、1~5日とばらつきのある結果となりました。幼虫を採取してから脱皮するまでの期間が個体によりバラバラなので、脱皮の遅い個体は水槽内で弱ってしまうということも結果のばらつきの原因になったかもしれません。
今年は幼虫を採取する時になるべく同定できるカゲロウを選び、種別に亜成虫、成虫の期間の違いについても観察しようとしましたが、人工的な環境の影響が大きかったのか、際立った違いは現れませんでした。採取した280頭の幼虫のうち、水槽内での羽化が確認できた個体は60頭で、21%の羽化率となりました。10月に採取した幼虫の羽化の数が少ないのは、気温と水温が急に下がったためと思われます。また、鬼怒川中流域におけるカゲロウ類の発生状況を見ても10月に羽化する数が減っていることがわかります。
羽化したエルモンヒラタカゲロウの雌雄の比率については、オスが26頭、メスが5頭と圧倒的にオスの方が多くなりました。しかし、昨年までのライトトラップによる発生状況の調査では、H6年ではオス38%メス62%、H7年ではオス41%メス59%、H8年ではオス27%メス73%と3年間ともメスの比率が高い結果となっています。なぜ人工的な環境のもとではオスの方が多いのかはよくわかりませんでした。
4.おわりに
今年はライトトラップによる調査をやめ、カゲロウの成虫、亜成虫の期間についての調査に集中した。この調査は今年で2年目であったため、昨年よりはスムーズに調査を行えたと思う。しかし、この調査は部室内の水槽を個人個人で観察し、記録するというものだったため、幼虫採集の時以外は班員がそろうということがなく、調査に関する話し合いや、班員同士のコミュニケーションが不足していたと思う。また、成虫の同定数も少なく同定能力の低下という問題点も残った。
最後に生物研究会顧問の中村先生をはじめ調査に協力してくれた会員の皆さんに感謝の意を表し終わりとする。